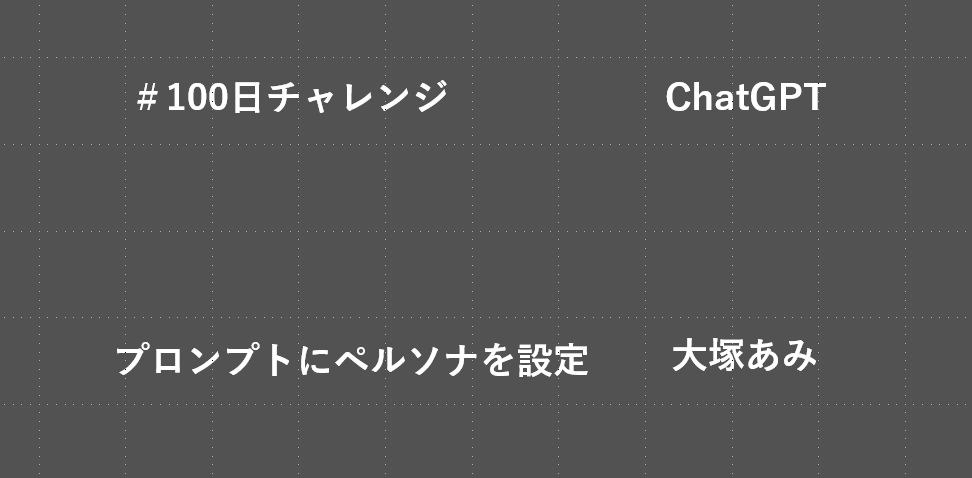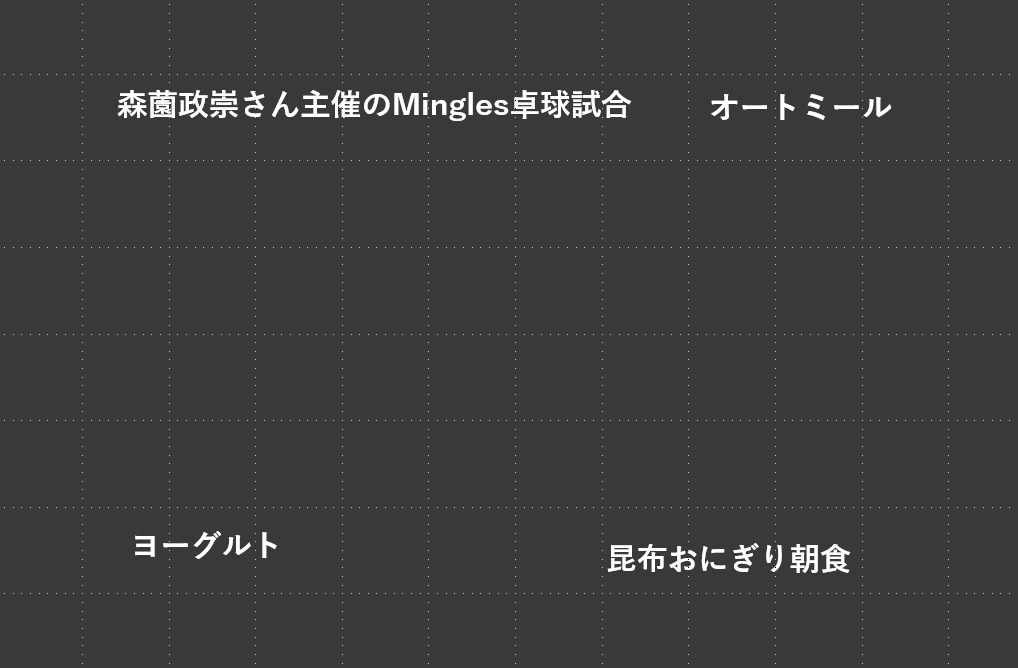Googleの生成AI「Gemini」を使って、note「よろず 環・境・研」にAIプログラミング(Tensorflow)環境構築を行った経験を基に、noteに掲載するGeminiの記事を書き始めたのが2月16日。その翌朝に、読売新聞オンラインに、「生成AI使い100日チャレンジ!怠け者・大学生の人生が変わった」の記事が掲載されたことを知りました。大塚あみさんがが中央大学4年生の時の経験を基にした記事です。既に、日経BP社から「100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった」というタイトルの本が出版されています。

#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった [ 大塚あみ ]
聞き手である読売新聞メディア局 永原香代子氏による記事の概要を下記にまとめました。
・チャットGPTへの質問の仕方について時間をかけてリサーチした結果、いわゆる「ペルソナ」を設定することで、無機質だった文章に味が加わることを知り、「チャットGPT最高!」と思った。
・大塚さんは2001年生まれ。Z世代の大学生に当たるが、2023年春の授業でチャットGPTに出会った。
・授業中、内緒でチャットGPTに聞きながらオセロ風ゲームを作ったのが教授に褒められ、論文を書き、学会で発表と、トントン拍子に話が進んだ。
・学会発表の機会なんて、きっと一生ないだろうなあと思い、せっかくのチャンスだからいい加減なことはしたくなかったので、発表原稿を作るのに30時間もかけた。
・1日1本のソフトウェアを100日間連続で作るというイベントをX(旧Twitter)で開始したところ、応援してくれる人が増えて引くに引けなくなり、ときには、プログラムのコードを書くのに1日10時間以上もかけて、ついにやり遂げた。
・最初は「Xに投稿する当日にチャットGPTに頼り切る」だったのが、100日を終了する頃には「前もって段取りを考えておく」という使い方から、「回答を予想しながらなるべく具体的に質問する」ように変わって行った。
・生成AIがあれば、人に仕事を頼むよりも自分でやった方が早いけれど、生成AIをパソコンのような道具として使いこなせるように使い手が変わって行く必要がある。
・自分で試行錯誤をしながら学んできたことを記録した300ページのメモが役に立った。今回の著書の土台にもなった。
・昨年12月に合同会社を設立した。開発者としても研究者としても始めたばかりだが、自分のパーソナリティーを前面に押し出して、仕事を頑張っていきたい。
元々ポテンシャルがあったと思いますが、2年足らずの間にとても鍛えられ、成長なさったのだと思いました。「GPTへの質問の仕方について時間をかけてリサーチした結果、いわゆる「ペルソナ」を設定することで、無機質だった文章に味が加わること」を早い段階で見つけた目の付け所や、ソフトウェア開発1日1本を100日続ける宣言をしてやり遂げた「有言実行」の誠実さとパワーがすごいと思います。
noteに掲載するGminiの記事を書きかけた私ですが、半世紀若い大塚さんの本を読んで、私の半世紀の人生の付加価値を確認してから記事を書こうと思い直しました。若い人と競争するのではなく、経験に基づいた違った視点を持てるかどうかの確認です。
by ウェルビー